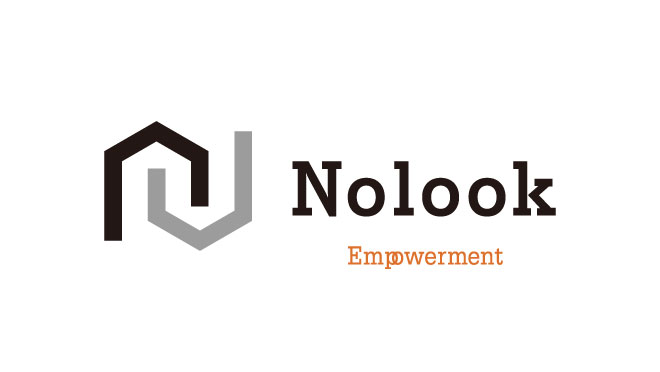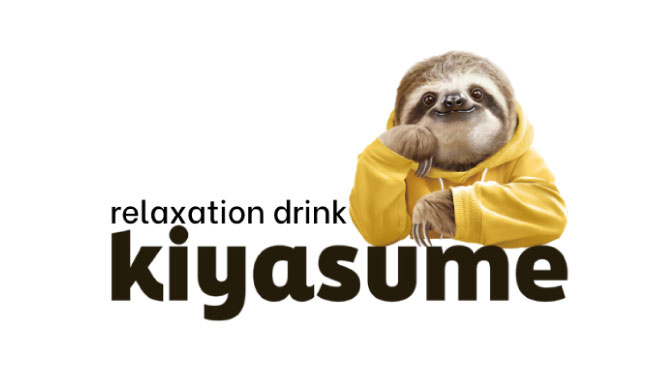COLUMN
コラム 〜マラソン豆知識〜
マラソンで上下動が走りに与える意外な影響とは?

日々マラソン大会に向けてトレーニングに励んでいるランナーの皆さんの中には、「もっとラクに走れたらいいのに」と感じたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、「後半に足が止まってしまう」「フォームが崩れてペースが落ちる」といった悩みに心当たりがある方も多いのではないでしょうか?
こうした、走りの課題に対し、多くのランナーはフォーム改善、トレーニングの強化、シューズ選び、補給戦略など、さまざまな工夫を重ねています。もちろん、それらはどれも大切な取り組みです。しかし、意外と見落とされがちでありながら、マラソンパフォーマンスに深く関わる重要なポイントが「上下動(Vertical Oscillation)」です。
上下動とは、走行中に体が上下にどれだけ動くか(揺れるか)という動きの幅を示す指標で、特に重心(骨盤周辺)が上下にどれほど移動するかを意味します。この上下動が大きくなりすぎると、身体が上下に跳ねている分、前進に必要なエネルギーが分散されてしまい、効率的な走りができなくなってしまうのです。
たとえば、同じペースで走っているのに、なぜか疲れやすい…という方は、知らず知らずのうちに上下動が過剰になっている可能性があります。逆に言えば、上下動を適正に抑えることで、少ない力でより長く、より速く走れる“省エネフォーム”を手に入れることができるのです。
GPSランニングウォッチの普及により、上下動の数値を簡単に可視化できるようになった今こそ、自分のフォームを見直す絶好のチャンス。今回は、上下動の基本知識から、理想的なフォームのあり方、改善のためのトレーニング方法まで、あらゆる角度から解説していきます。
マラソンで自己ベストを更新したい人、完走をよりラクに達成したい人、レース終盤での失速を減らしたい人——すべてのランナーにとって、この記事がフォーム改善のヒントとなっていただければと思うので是非参考にしてみてください。
上下動とは? — 走りの中の“隠れたエネルギー浪費”
今回はマラソンの上下運動について詳しくご紹介しますが、まず上下動とは、ランニング中の体(主に骨盤周辺)の上下方向への動きの幅を指します。最近のGPSウォッチ(GarminやPolarなど)には、上下動を数値化して表示してくれる機能もあり、たとえば「上下動7.5cm」などと表示されます。
上下動が大きい場合、足が地面を強く蹴り上げすぎていたり、姿勢のバネを使いすぎて跳ねていたりします。一見、力強い走りのように見えますが、上下に跳ねている分、前への推進力にはなっておらず、重力に逆らう無駄な動きになっているのです。
■理想的な上下動の目安
・一般的に5〜8cmが適正範囲
・エリートランナーの上下動は4〜6cm程度
・過剰な上下動(9cm以上)はエネルギー効率が低い可能性大
この数センチの違いが、42.195kmという距離を走り切るうえで大きな差となって表れてくるのです。
なぜ上下動を抑えるべきなのか?
上下動を抑えることで得られるメリットは、単なる「フォーム改善」だけにとどまりません。マラソン完走や自己ベスト更新を狙う上で、次のような実質的な効果があります。
■エネルギー効率の向上
上下方向への動きが少ないということは、それだけ重力に逆らう力を必要とせず、前への推進にエネルギーを集中できるということ。
同じペースでも「楽に走れる」と感じるようになるのはこのためです。
■足への衝撃が減少
上下動が大きいということは、着地のたびに足へ強い衝撃がかかっている証拠でもあります。上下動を減らすことで、膝や足首、股関節への負担を軽減し、ケガ予防にもつながります。
■ペースの安定と後半の粘り
上下動を抑えたフォームは、体幹が安定しているためフォームのブレが少なく、結果的にペースの維持や後半の失速防止にも効果的です。フォームが乱れると体力も余計に消費されてしまうため、フルマラソンでは致命傷となりかねません。
上下動が大きくなる原因とは?
多くのランナーが知らないうちに上下動の大きなフォームになっているのには理由があります。つぎに上下動が大きくなる主な原因を見ていきましょう。
■ピッチ(歩数)が少ない
1分間あたりの歩数(ピッチ)が少ないと、一歩一歩を大きく跳ねるように走るフォームになりがちです。ピッチを増やすことで自然と上下動が減る傾向にあります。
■接地位置が体の前になっている
脚が体の重心より前に出て着地する「オーバーストライド」の状態は、着地時の衝撃が大きく、上下動も増えやすいフォームです。
■骨盤・体幹が弱い
骨盤や体幹が不安定だと、体全体がブレてしまい、地面からの反発をうまく推進力に変えられません。結果として、上下方向の力が逃げてしまいます。
■靴のクッション性に頼りすぎ
厚底シューズやクッション性の高いシューズは、衝撃吸収の面で優れていますが、それに甘えてフォームが雑になると、上下動が大きくなってしまうことも。
理想的な上下動とは? — 上下に「揺れない」走り
ここまでは主に上下動を抑えるべき理由と、上下運動が大きくなる理由をご紹介しましたが、どのようなフォームが理想的な上下動を生み出すのでしょうか?
ポイント1:体幹がブレない
上下動を減らすには、体幹の安定が絶対条件。走行中も背筋を伸ばし、骨盤を立てた状態を保つことで、エネルギーのロスを最小限にできます。
ポイント2:接地は「重心真下」
足は体の重心の真下に着地させましょう。前に出すほど減速を生み、上下動も増えます。小刻みなピッチで、足を真下に落とす感覚が大切です。
ポイント3:視線は遠く、背筋を伸ばす
前かがみや顎が上がった姿勢は、重心がブレる原因に。視線は15〜20メートル先を見るようにし、頭から骨盤までが一直線になる姿勢を意識しましょう。
上下動を改善するためのトレーニング方法
上下動を改善するには、日常のランニングに加えて、以下のようなトレーニングを組み込むことが効果的です。
ここからは、上下動を改善するおすすめトレーニング方法をご紹介します。
■体幹トレーニング
・プランク(フロント・サイド)
・バードドッグ
・デッドバグ
体幹の筋肉を安定させることで、走行中のブレを防ぎます。
■骨盤・股関節の可動域強化
・ヒップリフト
・ワイドスクワット
・ランジ系トレーニング
骨盤まわりの筋肉(中臀筋・腸腰筋)を強化することで、地面からの反発をうまく前方へ変換できます。
■ドリル系ランニングフォーム練習
・スキップ走(低く跳ねる)
・トゥータッチ(つま先着地の感覚)
・ハイピッチドリル(180spm以上)
神経系のトレーニングとして、ピッチや着地感覚を改善できます。
■坂道トレーニング
登り坂を使ってのランニングは、自然とピッチが上がり、上下動が抑えられるため、感覚をつかむのに適しています。

まとめ
今回はマラソンの上下動についてご紹介しましたがいかがでしたでしょうか?
上下動という言葉を初めて意識した方も多いかもしれません。しかし、この「上下にどれだけ跳ねているか」という一見小さな動きが、実はフルマラソンにおけるタイムや走行中の疲労感、そしてフォームの安定性にまで深く影響しているのです。
上下動が抑えられたフォームは、身体のエネルギーを無駄なく前進に活かす“効率的な走り”を生み出します。さらに、着地時の衝撃が軽減されることで膝や足首への負担も少なくなり、怪我の予防やパフォーマンスの安定にもつながります。
もちろん、上下動を意識したからといって、すぐに完璧なフォームになるわけではありません。体幹の筋力強化、骨盤の安定、ピッチの見直し、正しい接地位置など、改善にはいくつかのステップが必要です。しかし、これらの地道な取り組みを積み重ねることで、あなたの走りは確実に変わっていくはずです。
マラソンとは、体力だけではなく技術と知識を積み上げていくスポーツです。上下動を意識したフォーム改善は、まさにその“知のトレーニング”のひとつ。今日から少しずつ、あなたの走りに変化を加えてみてください。それが、自己ベストを更新する最短ルートになるかもしれませんね。
PICK UP EVENTS 注目イベント
FAQ よくあるご質問
マラソン大会のお申し込み等について
マラソン大会の開催等について
マラソン大会当日について
UP RUN CONTENTS
SPONSOR 協賛
SNS

こんにちは
— UP RUN実行委員会 (@uprun_twx) January 6, 2026
本年も皆様のご愛好お待ちしております
さて今週のアップランマラソン大会は
10日
第27回UPRUN赤羽荒川
第64回スポーツメイトラン松戸江戸川河川敷
11日
第81回UPRUN新横浜鶴見川
2026所沢航空記念公園マラソン
12日
第28回UP RUN東大島小松川公園
第182回スポーツメイトラン皇居 pic.twitter.com/lLouZySskn
Warning: file_get_contents(/home/bridgeship/up-run.jp/public_html/wp-content/themes/up_run/inc/functions/svgs/front_logo_vertical.svg): Failed to open stream: No such file or directory in /home/bridgeship/up-run.jp/public_html/wp-content/themes/up_run/inc/functions/svgs/index.php on line 9