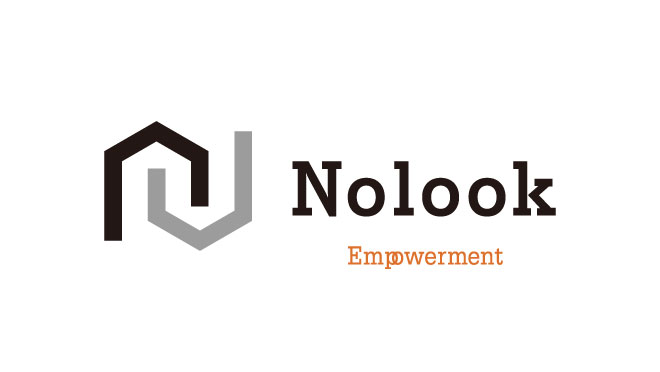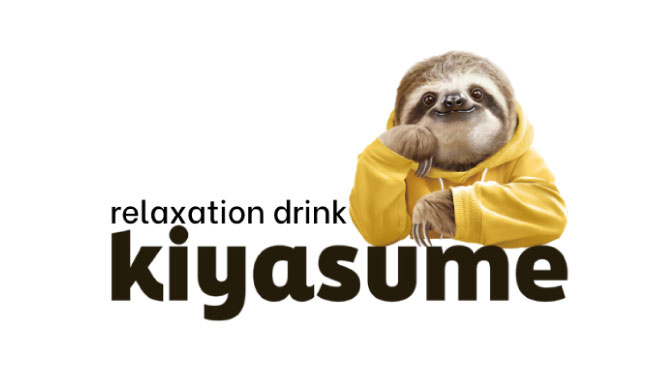COLUMN
コラム 〜マラソン豆知識〜
【保存版】マラソンの「ネットタイム」と「グロスタイム」の違いとは?意味・使い分けを徹底解説

マラソン大会に出場するランナーの中にはベテランランナー~ビギナー、初めてという方まで様々なクラスのランナーが参加されるかと思います。
その中で、マラソン大会に出ると、完走後に「ネットタイム」と「グロスタイム」という2種類の記録が表示されているのを目にすることがあります。特に初めて大会に参加した方の中には、「どちらが本当の自分のタイム?」「なぜタイムが2種類あるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
実はこの2つのタイムは、どちらかが正しくてどちらかが間違っているというわけではありません。それぞれに明確な意味と目的があり、ランナーの立場・大会の性質・表彰の有無・記録の認定などに応じて使い分けられています。
例えば、市民ランナーが自己ベストを更新したい場合、重要なのはネットタイム。一方で、上位入賞や公認記録を目指す競技者にとっては、グロスタイムが基準になります。
この違いをきちんと理解しておくことで、記録の受け止め方や目標設定がより明確になり、練習の質やモチベーションにも好影響を与えてくれるでしょう。特に近年では、大規模大会が主流となり、数万人単位でランナーが走るケースも珍しくありません。そのような環境下では、「タイムの捉え方」一つで満足度が大きく変わってきます。
今回は、ネットタイムとグロスタイムの違いをわかりやすく整理し、それぞれがどのような場面で用いられるのか、さらにランナーとしてどのように活かすべきかを詳しく解説します。これから大会に出る方や、すでにランニングを楽しんでいる方も、ぜひ参考にしてみてください。
ネットタイムとグロスタイムの定義と違い
今回はネットタイムと、グロスタイムについてご紹介しますが、まずはそれぞれの定義を明確にしておきましょう。また、ネットタイムと、グロスタイムが使用される場面をそれぞれご紹介していきます。
■グロスタイム(Gross Time)とは?
スタートの号砲からゴールまでの合計時間のことです。すべての参加者に対して共通のスタート時刻が起点になるため、たとえスタートラインを越えるまでに時間がかかったとしても、タイムは号砲からの計測になります。
例:号砲が9:00に鳴り、ゴールしたのが11:00なら、グロスタイムは「2時間00分」となります。
■ネットタイム(Net Time)とは?
スタートラインを実際に通過した時点からゴールまでの時間です。個々のランナーのスタートタイミングが考慮されるため、実際に自分が走った時間をより正確に表しています。
例:号砲が9:00でも、スタートラインを越えたのが9:05で、ゴールが11:00であれば、ネットタイムは「1時間55分」になります。
■ネットタイムが使われる主な場面
ネットタイムは、次のような場面で活用されます。
・ランナー自身の記録として
多くのランナーは、自分の実力を測る指標としてネットタイムを使います。混雑やブロックの位置によってスタートに時間差があるため、公平な「実走行タイム」として重視されます。
・トレーニングやレース分析時に有効
ペース配分や走力を評価する際には、グロスタイムではなくネットタイムを用いたほうが、より正確な分析が可能になります。GPSウォッチなどの計測と合わせて使うことで、自身のペース感覚やレース戦略の課題が見えてきます。
■グロスタイムが使われる主な場面
グロスタイムは、以下のような公式・競技的な場面で使われます。
・表彰順位の決定
多くの大会では、表彰や順位の決定は「グロスタイム」ベースで行われます。これは、先頭集団の競り合いなど、競技としての公平性を保つためです。
特に上位を狙うエリートランナーや招待選手は、グロスタイムによって競り合うため、スタートロスを最小限にする位置取りが重要になります。
・公認記録や資格タイムの証明
日本陸連公認大会などでは、記録証明や資格タイムとして認定されるのはグロスタイムです。たとえば、他の大会の参加資格条件(○時間以内)を満たすためには、グロスタイムでの記録が採用される場合が多いです。
タイム差の発生とその理由とは
グロスタイムとネットタイムには、スタートライン到達までの時間差がそのまま反映されます。特に大規模大会では、スタート地点が非常に混雑しており、スタート号砲から数分~10分以上かかることもあります。
■スタート地点の「ブロック分け」が影響
一般的に、持ちタイムによってA~Hなどのスタートブロックに分けられます。速いランナーほど前方に配置され、記録がない・初参加のランナーは後方になります。
後ろのブロックになればなるほど、スタートライン到達までに時間を要するため、グロスタイムとの差が大きくなります。
・両方のタイムが表示される理由
多くの大会では、記録証や公式サイトなどで「ネットタイム」と「グロスタイム」の両方が表示されます。これは以下の理由によります。
ランナー本人の評価指標としてのネットタイム
競技結果や公認記録としてのグロスタイム
公平性・透明性の観点から、両者を明示する必要があるため
両方を見比べることで、自分がどれだけスタートでロスしたか、ペース配分に無理がなかったかなど、詳細なレース分析も可能になります。
ネットタイム・グロスタイムを活かすポイント
最後にネットタイムとグロスタイムを有効生かすポイントをご紹介します。
■ 自己ベスト更新はどちらを基準に?
記録として残す自己ベスト(PB:Personal Best)は、ネットタイムを用いる人が多いです。実際に自分が走った距離と時間を基準にしたほうが、実力の進歩を正しく測れるためです。
ただし、資格記録や公認タイムはグロスでの提出が求められる場合もあるため、目的に応じて使い分けましょう。
■ エリートを目指すならグロスタイム重視
大会上位や入賞、陸連公認記録を目指す場合には、スタート位置やロスタイムを最小限に抑える戦略が重要になります。つまり、グロスタイムで戦うレース展開が求められるということです。

まとめ
今回はネットタイムとグロスタイムについてご紹介しましたがいかがでしたでしょうか?
マラソンのネットタイムとグロスタイムには、それぞれ明確な役割があります。
【目的と使用するタイム】
自己記録の更新:ネットタイム
表彰順位・公認記録:グロスタイム
レース戦略の分析:ネットタイム
大会での正式記録:グロスタイム
ネットタイムは、「自分が本当に走った距離と時間」の証として、非常に有用なデータです。たとえグロスタイムでは目標に届かなくても、ネットタイムで自己ベストを達成していれば、自分の成長を誇ることができます。
一方で、グロスタイムは「競技者としての正面勝負」において非常に重要です。公認記録や入賞を目指すようなレベルでは、ネットタイムよりもグロスタイムが絶対的な基準となります。だからこそ、スタートブロックの位置取りや、スタートロスの最小化といった戦略が求められます。
マラソンは、「他人との競争」であると同時に、「自分自身との戦い」でもあります。タイムの見方を理解し、自分にとっての本当の目標に沿って記録を活用することで、より深くマラソンの魅力を感じることができるでしょう。
大会後の記録証に刻まれる「2つのタイム」。その意味を正しく知っていれば、ゴールしたその瞬間の感動も、きっと何倍にも大きくなるはずです。
PICK UP EVENTS 注目イベント
FAQ よくあるご質問
マラソン大会のお申し込み等について
マラソン大会の開催等について
マラソン大会当日について
UP RUN CONTENTS
SPONSOR 協賛
SNS

こんにちは
— UP RUN実行委員会 (@uprun_twx) February 9, 2026
2月9日誕生花はキンセンカ
花言葉は【忍耐】【慈愛】
さて今週のアップランマラソン大会は
11日
第74回UPRUN府中多摩川風の道マラソン
14日
第44回UP RUN彩湖マラソン
第54回スポーツメイトラン川崎多摩川マラソン
15日
海の公園マラソン2026
第185回スポーツメイトラン皇居マラソン pic.twitter.com/CGMSFkzUlz
Warning: file_get_contents(/home/bridgeship/up-run.jp/public_html/wp-content/themes/up_run/inc/functions/svgs/front_logo_vertical.svg): Failed to open stream: No such file or directory in /home/bridgeship/up-run.jp/public_html/wp-content/themes/up_run/inc/functions/svgs/index.php on line 9