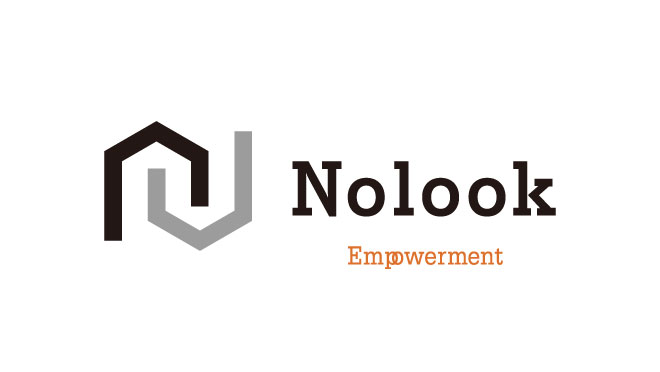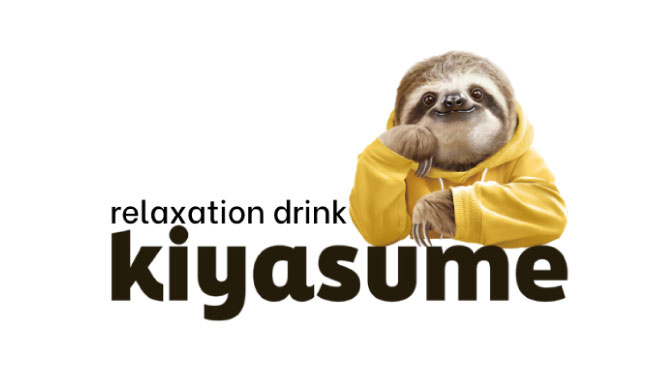COLUMN
コラム 〜マラソン豆知識〜
マラソンと『乗り込み』とは?マラソンとの関係性を徹底解説

日々マラソン大会に向けてランナーの皆さんは様々なトレーニングメニュー行っているかと思います。
マラソンは、42.195kmという距離そのものの過酷さだけでなく、そこに至るまでのプロセスによって大きく結果が左右されるスポーツです。特に市民ランナーにとって、レースで満足のいく結果を出すためには、単純な「走行距離の多さ」や「スピード練習の強度」だけではなく、“いかにして身体にマラソンの疲労感を染み込ませるか”という、実戦的な視点が重要になってきます。その鍵を握るのが、今回ご紹介する 「乗り込み」 です。
「乗り込み」という言葉は、特に長距離界ではよく使われる表現で、「走り込むこと」や「練習量を積むこと」だけを意味しているように見えます。しかし実際は、ただ長い距離を走るだけでも、闇雲に週の走行距離を増やすだけでもありません。
乗り込みには、ランナーがマラソンの“持久力と筋持久力の強化”“代謝の効率化”“脚の耐久性向上”“有酸素システムの拡大”といった、いわばマラソンの本質的な強さを積み上げるための明確な狙いが存在しています。
一方で、「乗り込みすぎて故障した」「疲労が抜け切らず逆に調子が落ちた」という声が多いのも事実です。乗り込みは、的確に行えばレースで大きなアドバンテージとなりますが、間違った方法で行うと、怪我や慢性疲労・パフォーマンス低下を招きかねません。
だからこそ、乗り込みの正しい方法やコツを理解することは、マラソンに挑むランナーにとって欠かせない武器となるのです。
今回は、「乗り込み」の本質的な意味から、失敗しないポイントまで様々な視点から乗り込みについてご紹介します。
日々の練習に迷いを感じている方、なかなか結果が出ず悩んでいる方、レースの後半に失速してしまう方にとって、乗り込みの理解は間違いなく強力な助けになるでしょう。
「乗り込み」とは何か?
まずは“乗り込み”という言葉が何を示すのか、その本質を理解することが重要です。ここを誤解したまま練習すると、距離だけが増えて効果が伴わなかったり、最悪の場合はケガにつながるリスクがあります。安全かつ効率的に強くなるためにも、最初に正しい定義を押さえておきましょう。
一般的に「乗り込み」とは、「長い距離を走ること」や「練習量を増やすこと」と表現されがちですが、実際にはそれだけでは不十分です。乗り込みの本質は“疲労の蓄積と適応を計画的に行うこと”にあります。つまり、ただ走る量を増やすのではなく、マラソンに不可欠な有酸素能力・脚の耐久性・代謝効率を高めるための体系的なトレーニングなのです。
■乗り込みは「量」×「質」×「継続」で決まる
・量(走行距離)
週100km以上が必要というイメージがありますが、それは上級者の話。
大切なのは「自分比」で増やすことです。
・質(ペース・意図)
“ゆっくり長く走るだけ”は乗り込みとして不十分。
LSD・Eペース・Mペースを組み合わせる必要があります。
・継続(週単位・月単位)
単発のロング走ではなく、「2〜6週間継続する」ことで効果が現れます。
つまり乗り込みとは、“計画的に疲労をためて、その疲労に身体を適応させる練習”なのです。
乗り込みがマラソンに必要な理由
では、なぜこれほどまでに乗り込みが重要視されるのでしょうか。
ランニングというスポーツは“走る”というシンプルな動作を繰り返すだけに見えて、実際は多くの生理的要素が複雑に絡み合っています。マラソンの後半で粘れるかどうか、失速するかどうかは、この乗り込みの質と量によって大きく変わります。ここでは、その理由をひとつずつ明確にしていきます。
■有酸素エンジンが拡大する
乗り込み期に継続して走ることで、心肺機能の向上ミトコンドリア量の増加、脂質代謝の改善が進み、マラソン後半で粘れる身体になります。
■脚の耐久性が向上する
マラソン後半は“脚”が理由で止まるランナーが多い。乗り込みは、大腿四頭筋、ハムストリングス、臀筋、足底筋などの耐久性を上げ、脚が売り切れにくくなります。
■乳酸の処理能力が高まる
長い時間走り続けることで、乳酸代謝能力(LT付近の能力)が向上。
レースの巡航ペースが楽に感じられるようになります。
市民ランナーのための安全な乗り込み方法
乗り込みの重要性を理解したら、次に大切なのは“安全に、かつ確実に”実践する方法です。特に市民ランナーにとっては、仕事や家庭との両立、疲労管理、ケガのリスクなど、多くの制約の中で練習を積む必要があります。そのため、闇雲に距離を追うのではなく、自分の身体に合わせた乗り込みの進め方を知ることが成功の鍵になります。ここからは実践的で再現性の高い方法をご紹介します。
■週の走行距離は「15〜25%アップ」が目安
急上昇させると故障の危険が高まるため、徐々に増やす“漸進性”が絶対ルール です。
■ロング走(25〜35km)を軸にする
乗り込み期の中心はロング走。
ゆっくり(Eペース)25〜35kmを週1回。
■2部練を取り入れる
距離を増やしたい場合、一度に頑張るのではなく
朝:ゆっくり10km
夜:ゆっくり8km
のように分散することで安全に走行距離を積めます。
■疲労抜きジョグを必ず入れる
「毎日頑張る」のは乗り込みとは異なる。
心拍数を抑えたジョグを挟むことで、疲労蓄積を“コントロール”できます。
レース前の乗り込みスケジュール
乗り込みはただ続ければよいというものではありません。特にマラソンはレース当日の状態がすべてであるため、いつ乗り込みを始め、どこで終わらせるかが非常に重要になります。適切なタイミングでピークを作り、疲労を抜き、レース当日に最高のパフォーマンスを発揮するためにも、時期ごとの練習設計を理解することが欠かせません。
■レースの4〜6週間前:乗り込み期のピーク
走行距離:最大
ロング走:2〜3本
Mペース走:1週間おき
この期間がマラソン力を最も底上げします。
■レースの3週間前:調整への橋渡し
乗り込みの終わり部分。
疲労がピークに来ますが、ここを乗り越えると一気に仕上がります。
■レース前2〜1週間:テーパリング
乗り込みは完全終了。
走行距離は徐々に落とす一方、“軽く走ることで調子を整える”時期になります。
乗り込みで失敗しないためのポイント
乗り込みは効果が高い反面、間違えると大きなリスクを抱える練習でもあります。実際、多くのランナーが、“乗り込み期に故障してしまう”、“疲労が抜けず調子を落とす”、という経験をしており、正しい管理が求められます。ここでは、乗り込みを成功させるために避けるべき落とし穴や、気をつけるべきポイントをご紹介します。
■距離だけに固執しない
疲れ切るまで走ることが目的ではありません。「質の高い疲労」を溜めるのが乗り込みです。
■睡眠と栄養を最優先する
乗り込み期は、たんぱく質、糖質、鉄分、睡眠時間を特に意識しましょう。
■ペースは普段より遅くてOK
ゆっくり走ることに抵抗があるランナーが多いですが、乗り込みでは Eペース(会話できる強度)が最適 です。
■痛みが出たら“中断”が正解
乗り込み期の故障は長引くため、痛みは放置しないことが鉄則です。

まとめ
今回がマラソンの乗り込みについてご紹介しましたがいかがでしたでしょうか?
乗り込みは、マラソンに特化した“本質的な強さ”を作るための最重要練習です。しかし、量をこなすだけではなく、目的を理解し、計画的に疲労を蓄積させ、回復を挟みながら継続させることに意味があります。ローリスクで、かつ最大の効果を引き出すためには、「漸進的に距離を増やす」「ロング走を軸にする」「疲労抜きを組み合わせる」「栄養・睡眠を徹底する」ことが欠かせません。
乗り込みはマラソンを“走り切るための土台”であり、“後半の失速を防ぐ最大の武器”でもあります。
正しい理解と実践によって、あなたの走力は間違いなく次のレベルへ進むでしょう。
PICK UP EVENTS 注目イベント
FAQ よくあるご質問
マラソン大会のお申し込み等について
マラソン大会の開催等について
マラソン大会当日について
UP RUN CONTENTS
SPONSOR 協賛
SNS

こんにちは
— UP RUN実行委員会 (@uprun_twx) February 16, 2026
2月16日の誕生花は月桂樹
花言葉は【勝利】【輝ける未来】
さて今週のアップランマラソン大会は
21日
UPRUN皇居
スポーツメイト府中
22日
UP RUN 二子新地・皇居
スポーツメイトラン東大島
23日
2026渡良瀬遊水地ウインターマラソン
詳細は画像でご覧ください✨ pic.twitter.com/kHoxvuoAdv
Warning: file_get_contents(/home/bridgeship/up-run.jp/public_html/wp-content/themes/up_run/inc/functions/svgs/front_logo_vertical.svg): Failed to open stream: No such file or directory in /home/bridgeship/up-run.jp/public_html/wp-content/themes/up_run/inc/functions/svgs/index.php on line 9