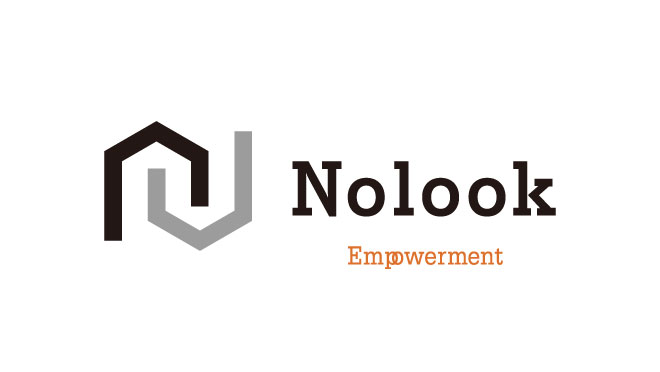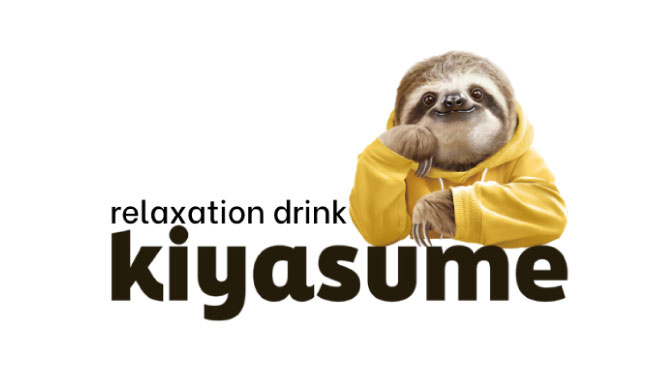COLUMN
コラム 〜マラソン豆知識〜
マラソンランナー必見!膝の外側に出る“違和感”は要注意?マラソンと腸脛靭帯炎の関係を徹底解説
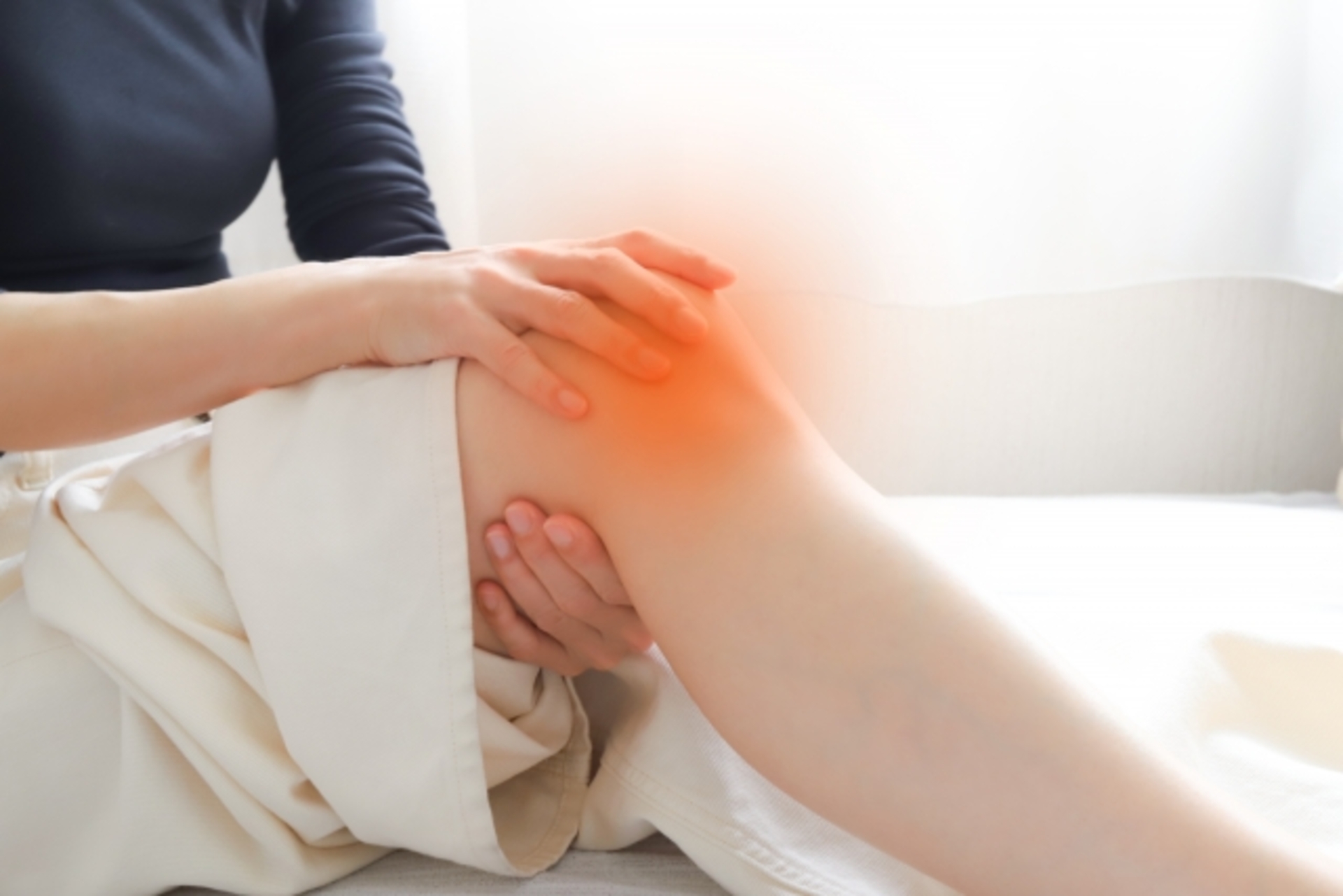
日々マラソン大会に向けてトレーニングに励むランナーの中には、「走っていて膝の外側がなんとなく張る」「違和感が出るときがある」という経験をお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか?
特に、レース本番やロング走の練習後に「あれ?膝が痛いかも…」と感じたなら要注意です。
膝外側の痛み・張りの原因のひとつとして、実は 腸脛靭帯炎(いわゆる “ランナー膝” の一種)が挙げられます。
今回は、マラソンという競技特性と腸脛靭帯炎との関連性を、症状・原因・予防・対策を“マラソン視点”でご紹介します。
現在悩んでいるランナーも、これから本格的にマラソンを始めたいランナーも今後の為に是非参考にしてみてください。
腸脛靭帯とは何か?
まずは、腸脛靭帯(iliotibial band:ITバンド)の構造と役割を整理し、なぜマラソンという運動形式でトラブルになりやすいかをご紹介していきます。
腸脛靭帯は、骨盤のあたり(大腿筋膜張筋・大殿筋など)から始まり、大腿部外側を通り、膝近くで停止する強靭な線維性組織です。この靭帯は、脚を走らせる際の膝の屈伸・着地・蹴り出しで外側に張力がかかりやすい構造を持っています。マラソンのように膝の屈伸運動と荷重移動を長時間・長回数にわたって繰り返す運動では、まさにこの腸脛靭帯が“使われ過ぎて摩擦・張力”を受けやすくなるのです。
また、腸脛靭帯が膝の外側、特に大腿骨外側上顆という骨の出っ張り部位を越えるあたりで、「摩擦・圧迫・張り」が発生しやすいことも指摘されています。ランニング中、膝を曲げ伸ばしする度にこの部位を“滑るように越える”動作があるため、適切なケアや走り方を備えておかないと、腸脛靭帯炎という症状を招きやすくなります。
このように、構造・走行動作・荷重条件のすべてが重なるマラソンという場面で、腸脛靭帯炎は“起こりやすい障害”となるわけです。
なぜマラソンでは腸脛靭帯炎が起きやすいのか
ここまでは腸脛靭帯炎についてご紹介しましたがここからは、マラソン・長距離ランニングの特性から「腸脛靭帯炎が起きやすい理由」をご紹介していきます。
■オーバーユース(使いすぎ)
マラソン練習では、毎週数十キロ・長時間のランニングが含まれ、膝の曲げ伸ばし・着地・反発が膨大な回数になります。この“反復荷重”が腸脛靭帯と骨の摩擦部位のストレスを増大させる典型的な原因です。特に「急に距離を増やした」「走る頻度を上げた」「疲労が残ったまま走った」などの場合、靭帯にかかる張力・摩擦機会が一段と高まります。
■着地の角度・走路・下り坂などの負荷条件
膝が約30°前後の屈曲をした状態で荷重が掛かると、腸脛靭帯が大腿骨外側上顆を“越える”動作時に摩擦が増すといわれています。ランニングではこの屈曲角が多く、特に「疲れて膝が曲がりきらない」「フォームが崩れた」「下り坂・硬い路面・不整地」などの条件下では負荷が強まることがあります。さらに、下り坂では膝への衝撃・屈伸が大きく、靭帯張力も増えるため、腸脛靭帯炎のリスクが顕著に上がります。
■身体のアライメント・柔軟性・筋力不足
膝・股関節・骨盤のアライメント(足の付き方・膝の向き・脚のブレ)が乱れている場合、腸脛靭帯に対する摩擦・張力が通常より高くなります。例えば、O脚・脚が外側にぶれる・骨盤が傾くなどがあると、膝外側の靭帯が“余計な引っ張り・擦れ”を受けやすくなります。また、臀筋・大腿外側(大腿筋膜張筋)・ハムストリングスの筋力・柔軟性が低いと、脚を安定させることができず、腸脛靭帯にかかる負荷を軽減できないまま走り続けることになります。
■マラソン特有の条件
マラソンならではの条件、例えば「長時間走る」「後半に疲れてフォームが乱れる」「大会やレースが近づいて量・強度を増やす」などは、腸脛靭帯炎を起こすリスクをさらに高めます。距離を急に増やしたり、坂道・スピード練習を多用したりすると、身体がまだ対応できていない状態で負荷をかけてしまうため、靭帯にとって“非常事態”となるのです。
以上を踏まると、マラソンという運動様式は、腸脛靭帯炎を引き起こす条件が揃いやすいと言えます。では次に、実際にどのような症状が出るのか、確認していきましょう。
症状、診断、その後の進行の流れ
腸脛靭帯炎になった場合に現れる典型的な症状、どのように診断されるか、進行するとどうなるかを次にご紹介していきます。
■症状
まず最初に現れるのは、ランニング中またはランニング後に「膝の外側(大腿骨外側上顆付近)に張り・違和感・軽い痛み」が出ることです。走り出してから一定距離走ったあたりで「あれ?外側がなんか張るな」と感じたら注意が必要です。最初は休めば回復することもありますが、放置するとランニング途中から痛みが出る、あるいは日常動作時にも張り・違和感が残るようになります。
■診断・検査
臨床的には、膝外側の圧痛・走行時、走行後の痛み・膝の曲げ伸ばし時の引っ掛かり感などを手がかりに診断されます。画像検査としては、レントゲンでは明らかな異常は出にくく、MRIで「大腿骨外側上顆近傍の滑液包の炎症所見」や「腸脛靭帯の肥厚」などが確認されるケースもあります。このため、走っていて膝外側に継続的な違和感がある場合には、専門機関への相談が推奨されます。
■進行の流れと注意点
初期段階では、距離を走ったあとに張りを感じて翌日には軽快することもあります。しかし、練習量を落とさず走り続けると、中期ではランニング中から痛みが出るようになり、着地・蹴り出しがスムーズにできずペースが落ちる・脚が重く感じるといった影響も出てきます。最悪の場合、歩行時・階段昇降時にも膝の外側が痛むようになり、日常生活にも支障をきたすようになります。特に、レース直前で無理をして走り続けると、一気に悪化して「次のシーズンまで影響が残る」こともあります。
マラソンランナーのための予防&対策
それでは最後に、マラソンを走るランナーが、腸脛靭帯炎を未然に防ぐための予防策をご紹介します。走りの質からケアまで多角的に捉えましょう。
■練習設計・走行量・ペース管理
まず、練習量(距離・時間・強度)は、自身の筋力・柔軟性・経験値に見合ったものであることが大前提です。急に距離を伸ばしたり、ペースを大きく上げたり、坂道や不整地ばかり走ることは「靭帯にとっての負荷アップ」に直結します。特にマラソンに向けて量や強度を上げる時期には、必ず“身体の準備度”を確認し、疲労が溜まっていたら量を抑える選択肢を持ちましょう。
■ストレッチ・筋力・柔軟性強化
腸脛靭帯と深く関連する筋・筋膜群(臀筋・大腿筋膜張筋・ハムストリングス・下腿外側筋など)を重点的にケアします。これらの柔軟性が乏しかったり、筋力が弱かったりすると、脚のブレ・不安定な接地・膝の外側への張力増に繋がります。具体的には、股関節外転筋・骨盤周り・体幹の筋トレ、脚外側のストレッチを日常的に取り入れ、脚全体を安定させることが重要です。
■シューズ・インソール・路面選び
走る環境・装備も大きく影響します。硬めの路面(アスファルト・コンクリート)や古くなった・横剛性の低いシューズでは、膝外側にかかる反動・衝撃が増え、腸脛靭帯への負荷も上がります。適切なランニングシューズを選び(クッション性・足型に合ったもの)、場合によってはインソール(足底板)を使って脚外側・膝外側をサポートしましょう。サポーターやテーピングも選択肢となります。
■ケア・休養・クロストレーニング
走った後のケアは軽視できません。必ずクールダウン・ストレッチ・場合によってはアイシング(膝外側部)を取り入れ、疲労・炎症を翌日に残さないようにします。違和感を感じた時に無理を続けると、痛みを長引かせる原因になります。休養日を確保し、心肺維持目的でクロストレーニング(水泳・エアロバイクなど)を活用することも有効です。特に痛みがある時には“脚に衝撃を与えない運動”に切り替える賢さが必要です。

まとめ
今回はマラソンと腸脛靭帯炎についてご紹介しましたがいかがでしたでしょうか?
長距離ランニング・マラソンは「脚・膝・身体を使い続ける」運動であるがゆえに、腸脛靭帯炎のような“膝外側のトラブル”が起きやすい環境にあります。しかし、逆に言えば「そのリスクを理解し、適切な対策を講じれば、痛みに悩まされずに走り続けることが可能」な障害でもあります。
特に、次の3点を意識しておけば、長く快適にマラソンに取り組める基盤となります。
・違和感・張り・軽い痛みを感じたら、早めにケア・調整を行うこと。
・臀筋・大腿外側・股関節・体幹など“身体の安定を担う部分”の筋力・柔軟性を高め、フォーム崩れを防ぐこと。
・シューズ・インソール・路面・走りの質など“脚外側にかかる負荷”を抑える工夫をすること。
マラソンは単に「どれだけ走るか」だけではなく、「どう走るか」「どのように身体を整えておくか」が大切です。腸脛靭帯炎は多くのランナーにとって身近な障害ですが、知識と準備があれば十分に防ぐことができます。次の大会や長距離走に向けて、膝の外側の違和感を感じたら、ぜひこの記事の内容を思い出していただければと思います。
PICK UP EVENTS 注目イベント
FAQ よくあるご質問
マラソン大会のお申し込み等について
マラソン大会の開催等について
マラソン大会当日について
UP RUN CONTENTS
SPONSOR 協賛
SNS

こんにちは
— UP RUN実行委員会 (@uprun_twx) February 16, 2026
2月16日の誕生花は月桂樹
花言葉は【勝利】【輝ける未来】
さて今週のアップランマラソン大会は
21日
UPRUN皇居
スポーツメイト府中
22日
UP RUN 二子新地・皇居
スポーツメイトラン東大島
23日
2026渡良瀬遊水地ウインターマラソン
詳細は画像でご覧ください✨ pic.twitter.com/kHoxvuoAdv
Warning: file_get_contents(/home/bridgeship/up-run.jp/public_html/wp-content/themes/up_run/inc/functions/svgs/front_logo_vertical.svg): Failed to open stream: No such file or directory in /home/bridgeship/up-run.jp/public_html/wp-content/themes/up_run/inc/functions/svgs/index.php on line 9